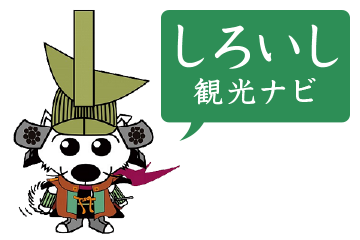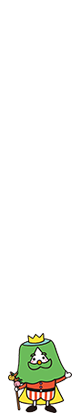宮城県白石市の観光情報紹介サイト「しろいし観光ナビ」
白石城周辺の歴史スポット(城の南側)
白石城周辺の歴史スポット(城の南側)


越河宿・斎川宿
白石城は、奥州街道の越河(こすごう)・斎川宿から北側10キロに位置し、仙台藩にとって重要な拠点であり、仙台藩を「守る」南の要塞の城という役割があったといえる。越河宿・斎川宿付近は道幅が極端に狭く、交通の要衝とされていた。

斎川宿 宿場町の風情を残している

あぶみずり坂
馬に乗るときに使う「鐙(あぶみ)」が両側の岩肌ですれてしまうほど細く急な山道だったため、「あぶみずり坂」と言われたという。
松尾芭蕉の「おくのほそ道」にも登場する。すぐ近くには源義経の身代わりとなってなくなった家臣・佐藤継信、忠信兄弟の妻をまつった「甲冑堂」があり、斎川宿にも近い。

佐藤継信、忠信兄弟の妻をまつった「甲冑堂」

傑山寺
片倉小十郎景綱が片倉家の菩提寺として創建。景綱の銅像や墓標の一本杉などがある。三代・片倉小十郎景長の父にあたる松前安広の墓や江戸時代に活躍した大相撲の力士・初代谷風の墓もある。
松前家の墓は、将棋型の墓石が立ち並んでいる。松前城主・松前慶広の五男・安広は片倉重長に仕え、重長の娘・喜佐と結婚し景長を設けた。安広の子広国は「伊達騒動」で活躍した。

景綱の銅像や墓標の一本杉

初代谷風の墓。この大きな石は生前谷風が運んできたという言い伝えがある。